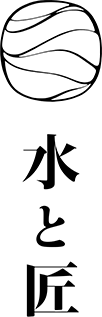いきおいよく墨が飛び散った襖絵の前の家族写真がかけられている。ふっくらとした奥さんに、良いおべべを着せられてきょとんとしている赤ん坊、ジャムバンドのドラマーのような野趣と洒脱さがまざった雰囲気の坊主頭の男性、そして分厚い瓶底メガネをかけた男。
キャプションには「光徳寺にて」とある。ということは、坊主頭の男性は光徳寺(文字に記事リンク)のご住職、襖絵は『華厳松』、メガネの男は棟方志功だ。
展示会場で目に入った写真にグっと心を掴まれて、写っている人の存在感が迫ってきた。福光に棟方志功が暮らしたこと、光徳寺の襖に絵を描いたこと、それが生活の中で建具として使われていたこと。話には伺っていた出来事が、実際にあったこととして精彩をおびてくる。そしてご住職の格好良さ。富山はお寺が文化をつくってきた土地だと感じるが、それはお坊さんが格好良いということなのか。
「小さい頃から父の仕事場には志功さんの作品がたくさんあって、わたしはなーんでこんなに棟方志功ばっかりなんだろうと思っていました。志功さんが福光に疎開していたことは大人になるまで知らなくて。これも最近知ったんですが、父が駆け出しの頃初めてもらった仕事が、光徳寺さんの志功さんの作品でした」

福光美術館の土居彩子(さいこ)さんは、福野(旧福野町。福光や城端と合併して南砺市になった)の出身で、実家は表具屋を営んでいる。土居さんは東京の美大を出たあとそのまま都内で働いていたが、震災が暮らしを見直すきっかけになり、家族とともに帰郷。その頃ちょうど募集のあった棟方志功記念館の職員に応募し、今は学芸員として働いている。
「ここで暮らし始めたら、芸術って何なんだろうって考えていたことの答えが足元に、志功さんや柳(柳宗悦)の言葉の中にあったことに気づきました。生活のなかに密着して、血となり肉となるようなものでなければ芸術とはいえない、芸術のための芸術っていうのは違うんだろうなあって」
言葉ではっきりとは捉えていなくても、幼い頃に触れていたものは、思いのほか自分の感性や人生の選択に大きな影響を与えている。無意識に引き寄せられている、と感じることもある。土居さんの個人史には、棟方がこの土地で生活していたこと、それが土地の人の暮らしに少なからず影響して縁が生まれていることが感じられて、胸が熱くなる。
知れば知るほど、棟方のことが大好きになるという土居さん。「棟方志功の福光時代」展を開催中の福光美術館にて、作品の変遷や棟方を語る上ではずせない「他力」についてお話を伺った。
南砺市立福光美術館は光徳寺にほど近い、木の匂いや鳥の声が心地良い森の中にある。福光時代に描かれたものを中心に棟方作品を多数収蔵、季節に応じて変わる常設展では常に棟方の作品を観ることができる。「棟方志功の福光時代展」ではさらに企画展示室も合わせた全館に棟方作品が展示され、創作の変遷をたどれる貴重な機会となっていた。
企画展にはそのほか柳宗悦や芹沢銈介といった民藝同人、ジョルジュ・ルオーの版画作品など、民藝ゆかりの地ならではのテーマにもとづいたものが催されており、その内容には地方だからと侮れない土地の文化度の高さがうかがえる。

この日は常設展示室に菩薩が書で表されたもの、企画展示室には版画で表されたものと、二つの「二菩薩釈迦十大弟子」を観ることができた。
菩薩が書で表された「二菩薩釈迦十大弟子」には、棟方が国際美術展で大賞を受賞する前段となる、劇的な逸話がある。
福光に疎開した頃の棟方はまだ広く名を知られておらず、戦火のなか版木を安全に保管できる状況にはなかった。空襲が激化する東京で駅に持ち込める疎開荷物は1日に5点だけ、美術品は後回し、生活必需品が最優先。無名作家の真っ黒な板切れが送れるはずがない。そこで棟方の奥さんは、背もたれ付きの椅子5脚の添え木として、両面に釈迦の弟子が彫られた版木5枚を梱包して真っ先に持ち込んだ。当時の大混乱の中で、その荷物は奇跡的に福光まで運ばれてくる。しかしその直後に東京大空襲が起き、暮らしていた家と版木は全焼。両脇の菩薩は燃えてなくなってしまう。駅で発送を待っていた他の荷物もほとんどが焼けてしまった。
「まるで菩薩様が弟子たちを守ったみたいですよね」
両脇の菩薩が彫り直されたのは福光への疎開後のこと。そして制作時から16年の時を経て、同作品はサンパウロ、ヴェネチア両ビエンナーレの版画部門で最高賞を受賞。棟方志功は世界のムナカタになった。今でも美術家としての評価は、日本国内よりも海外での方が高いという。
もし運び出しが間に合わなかったら、荷物がきちんと届かなかったら、作品を運び込める理解ある疎開先がなかったら。どのパーツが欠けても、後の大きな評価は得られなかった。作品が個人を超える大きな存在に守られていたと感じさせるエピソードだ。
「志功さんはピンチをチャンスにかえる、ということがたくさんあった人でした。たとえば志功さんには画家になりたいのに目が悪いという、致命的なハンデがありました。それが版画という表現方法に出会ったことで、ハンデではなくなるわけですね。目が見えないから心の中のイメージで描いていくところに、強いデザイン性が獲得される。志功さんの作品には、計算されつくしていない美しさ、作品が発するものすごい熱量を感じます」


福光時代の棟方は、お坊さんと常に交流していた。感銘を受けた言葉をその場で襖に書きつけてしまったという作品もある。
書かれている言葉は「宿業者是本能則感應道交」。宿業は人間の本能、無理に悩みを取り去ろうとするのではなく、悩みがあるからこそ仏様と感応できる。生まれつきの姿を深く自覚することで真実に出会えるとの意味で、目が悪いことと自分の罪業をからめ感じていた棟方がその特性に希望を見出すきっかけになったともいわれる。
「これだこれだ、自分の求めてたものはこれだ!って、吉田龍象さんの念仏道場(寺院の形をとらない教えを学ぶための場所)で、そこにあった墨でぶわあああっと描いちゃったそうです。ほんとうに心通い合うお坊さんはごく一部だったと思いますが、親しくなった方とはほんとうに親密にされていて。知源寺というお寺の今のご住職も、小さい頃は棟方が毎日来ていた、とおっしゃっていました」
福光では、子どもたちとの関わりも多くあった。棟方が住んだ家は小学校の横にあり、棟方はよく子どもたちが山へ写生に行くのについていった。
「志功さんは、うわあすっごいいい絵だなあ!仏様がいるなあ!って、とにかくわあわあ言ってまわるだけだったそうです。アドバイスじゃないんですよ。でもそれに元気づけられて、当時の子どもたち、今は齢80過ぎになっている方で、今も描いてるという人にけっこうお会いするんです」
今展示会期間中には、南砺市中の小学校5・6年生が全員、先生に引率されて美術館へやって来た。松の絵の前で「志功さんにとってはこれが松でした。何をどう感じるかはみんな違うけれど、自分の感じたことを大事にして、描きたいものをじゃんじゃん描きなさい」と棟方の“心”を伝えると、子どもたちの目はらんらんと輝き、わあああああっと歓声があがったという。

「福光時代は、お坊さんもそうなんですけど、そこに生活する人たちといっぱい接した時期なんだと思います」
小学校は現在では公園になり、広場のほとりに「鯉雨画斎(りうがさい)」と名付けられた棟方の家が今も残されている。名前の由来になった押入れの鯉の絵、トイレの菩薩様。とにかくどこにでも描いてしまったという棟方の暮らしが垣間見える。

「志功さんは、他力っていうことをずっと心に抱いていて、求めていたんですよね」
生まれ故郷の青森は寺院の多い土地で、信心深い祖母の影響もあり、幼い頃から信仰に親しんでいた棟方。東京にいる頃は知識として蓄えていた他力思想を、福光では毎日お寺に通い、地元の人たちに混ざり一緒に念仏をとなえ、土着の宗教人たちと深く交わることで肌身に学んだ。
「福光に来てから、力が抜けた作品になったって柳さん(柳宗悦)は仰るんですね。福光以前の作品は白黒はっきりしていて、力が漲っている。それはそれですごく素敵なんですけど、福光でつくられたものには力(りき)みがなくなって、泳ぐような、身を委ねている自由さがあるんです」
その違いは『二菩薩釈迦十大弟子』に歴然と表れている。弟子たちを構成する線はゴリゴリとして硬いが、福光時代以降に彫られた菩薩の線はふっくらとして丸みがある。また福光では戦後で版木が手に入らない中、木の命を生かそうと彫るところを減らした、黒い身体の表現がみられるようになる。さらにはそこへ刺青のような柄、縄文土器に似た紋様が彫られていく。


『歓喜頌』という作品の線は、世界各地にある伝統的な織物や焼き物を彷彿とさせる。棟方は「自分の仕事には自分で責任を持っていません、自分が背負い切れる程度の小さな仕事はしていません、もっともっと大きな力で仕事をしています」と言った。まさにその通りだったのだろう、匿名的な、その土地が生み出したとしかいえないような、プリミティブな力を背景に感じる。
裏側から彩色を施す技法によって、白い部分がより際立っている同作品は、ほわんと発光するメディアアートのようでもある。カンナをかけない版木の質感がそのまま現れた『道祖土頌』にも、土着的なエネルギーと、デジタルでクールな格好良さが同居している。
そうした魅力は「版木」「彫刻刀が描く線」といった“ものの性質”が、作品に現れるところからくるのではないか。
子どもたちが沸いたという『御松図』も、筆で顔料を飛び散らすという、物理法則が生む液体の軌跡を表現に引き込むものだ。棟方の作品には思考や知識ではないところで“ものの性質”がとらえられており、それがデザイン性の高さや、力強さと同居したかろやかさ、どことなく惹きつけられる愛嬌といった魅力につながっている。
「志功さんの肉筆画って暴れまくってるじゃないですか。それが下絵を描き、彫り、刷るっていう3段階を経ることで、だんだんおさまっていくんですよね。おさまりきらないエネルギーが版画になることによって、作品として凝縮されていく感じがありますね」

他力思想は、他力=自然の秩序を受け入れて身を任せ、大きな力の働きにのって生きることを説く。ものの性質とは、他力のひとつの現れだ。それは必ずしも自分の思い通りにならない不自由なものだが、その不自由を引き受けて創られるものは、自然そのものが持つ美の力を味方にできる。不自由を受けきることで、かえってのびのびとした自由さや、背景にある広大なものとの繋がりが獲得されるのだ。
そして、自分の身体も実は自然の一部である。生まれついた身体は、努力や環境次第で変えられることもあるが、どうにもならないこともある。福光での他力を体得する生活は、棟方の極度の近眼という自身の特性の肯定にも繋がったのではないか。
「志功さんがハチマキをしている写真、よくありますよね。あれ、汗っかきだからハチマキをしてるのかと思っていたんですが、よくみたら紙縒(こより:紙を縒ってつくったもの)なんです。だからあれは、しめ縄です。自分のなかに宿ってる仏様をまつって、その力でつくるという、そういう姿ですね」

さて、福光美術館には棟方と肩を並べるもうひとつの目玉がある。日本で有数の収蔵数を誇る、福光出身の日本画家、石崎光瑤(こうよう)の作品群だ。
光瑤は12歳で琳派に、19歳で円山・四条派の竹内栖鳳(せいほう)に弟子入りし、鮮やかな花鳥画を得意とした。自然を全身で感じられる登山を好み、明治42年には民間人として初めての剱岳登頂を果たしている。「実際にものを見たい」という情熱からインドへ出かけ、ヒマラヤ山脈にも登った。代表作の「燦雨(さんう)」はインドの風景に浸りきって帰ってきた後に描いた作品だ。
俯瞰、水平と、いくつも混ざり合う視点の自由さ。時間が描きこまれているような、遠近感とは違う奥行き。速度、温度、光、感覚に強く訴える線描の力。顔料の立体的な使い方。光瑤の作品を観るためだけでも足を運ぶ価値がある。

裕福な家庭に生まれ写実性に長けた光瑤の、観察眼に支えられた洗練の美。貧しさと目の悪さの中でもがいた棟方の、土着的で力強い美。
両者は対照的だが、自然への絶対的な信頼と憧憬は共通している。目指した場所への登り方は違っても、頂きから見た景色は案外近いものだったかもしれない。
最後に棟方を引き寄せた福光の魅力について、土居さんに聞いてみた。
「やっぱり人なんだろうなあって思います。光徳寺さんをはじめ、志功さんをいろんな人が助けてくれた。変人と思う人もたくさんいたんでしょうが、心の通いあう人がいた。そこにさらに、ふるさと青森に似た自然の風景があった。私自身も、福光の好きなところと聞かれて思い浮かぶのは人です。ご縁が生まれて、人が助けてくれる場所です」
写真:田中祐樹 文章:籔谷智恵

オフィシャルツアー
水と匠では福光美術館をはじめとする棟方ゆかりの地をご案内するオフィシャルツアーを実施しています。<棟方志功が暮らした民藝と発酵食の聖地で「土徳」に触れる>内容やスケジュールはお客様のご要望にあわせて変更可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォーム

南砺市立福光美術館
住所:富山県南砺市法林寺2010
電話:0763-52-7576
開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)
休館日:火曜日・年末年始(12/29~1/3まで)
(詳細はwebサイトを確認)
入館料:常設展 ■一般 310円 ■高大生 210円 ■小中学生 無料 企画展は内容により異なる
https://nanto-museum.com/

棟方志功記念館「愛染苑」
住所:富山県南砺市福光1026-4
電話:0763-52-5815
休館日:火曜日・年末年始(12/29~1/3まで)
入館料:常設展 ■一般 310円 ■高大生 210円 ■小中学生 無料